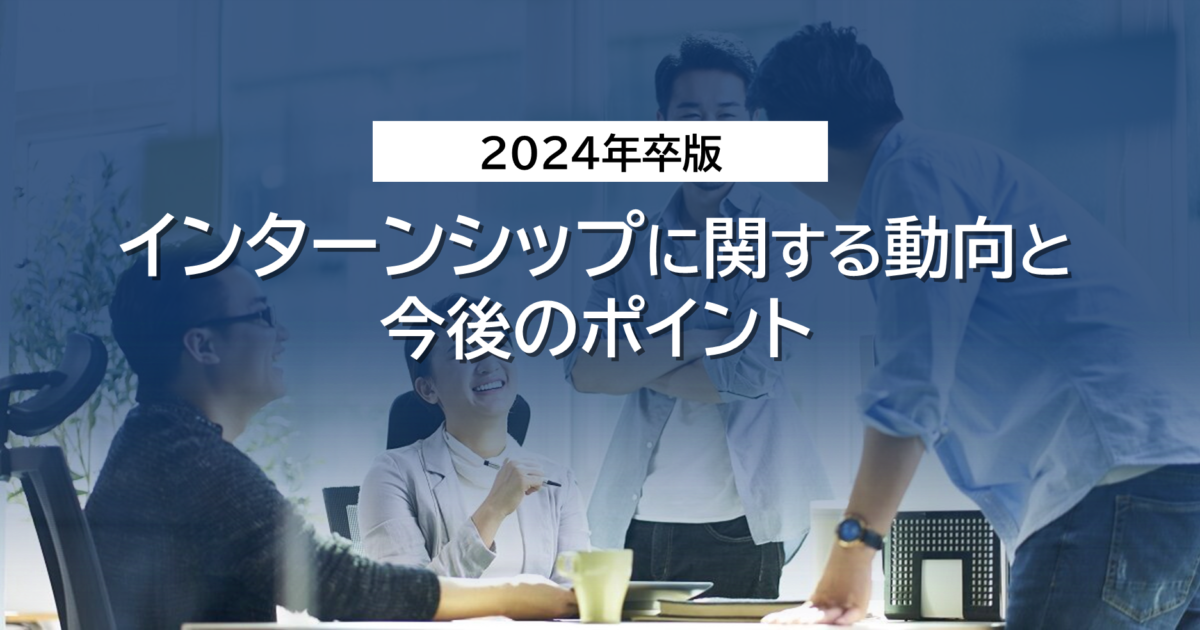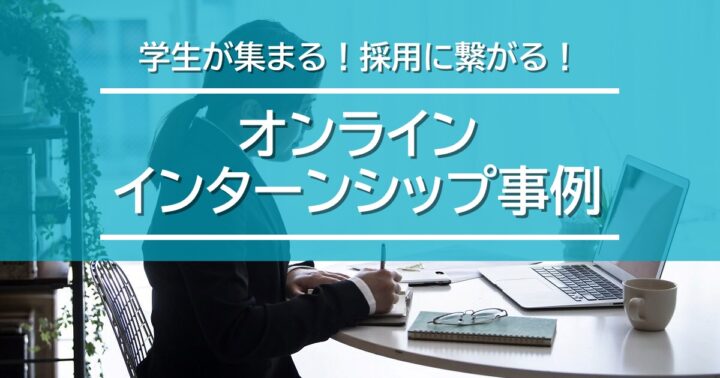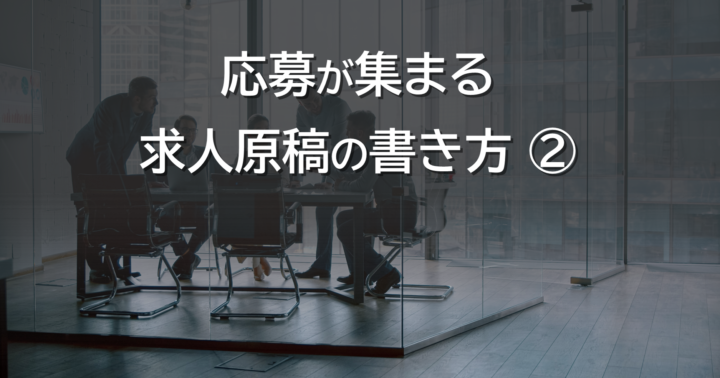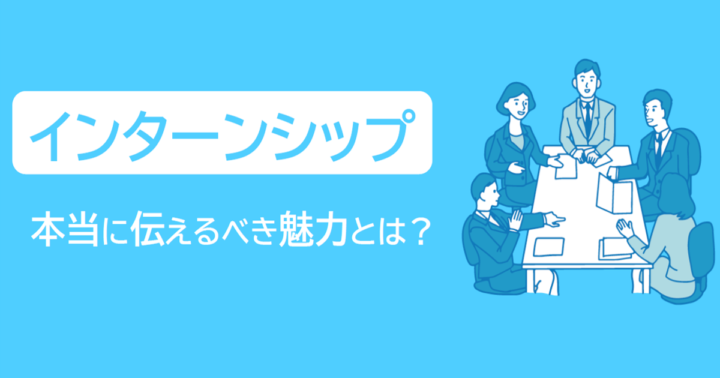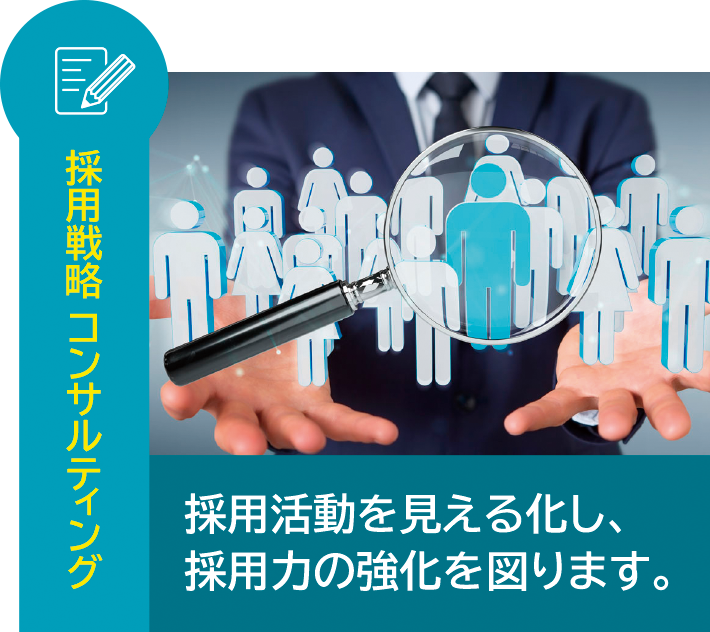企業・学生ともに、昨今年々重要視されているインターンシップ。今や、インターンシップは採用活動における主戦場となっています。
そこで、今回のコラムでは株式会社マイナビの最新調査をもとに、インターンシップに関する学生動向と今後のポイントについて解説します。
※出典;株式会社マイナビ「大学生インターンシップ・就職活動準備実態調査(2025年1月)」(s-internship-26-12-001-2.pdf)
もくじ
2026年卒全体のインターンシップ動向
インターンシップの参加率と参加時期
まず、今の学生はどの程度インターンシップに参加しているのでしょうか?
同社の調査によると、2024年12月時点での累計参加率は87.2%と前年を上回って推移しており、例年以上に多くの学生がインターンシップに参加していることが分かります。
また、インターンシップに参加した時期を聞いたところ、最も多い時期が9月(71.4%)となっており、主には大学2年生または学院1年生の6月からインターンシップに参加し始める学生が多いことが伺えます。
インターンシップの参加社数と今後の参加意向
次に、インターンシップの参加社数を見ていきましょう。
まず、文系学生のインターンシップ参加社数ですが、1社~3社のインターンシップに参加した学生は3割程度となっています。また、理系学生の中で1社~3社のインターンシップに参加した学生は4割程度と、やや理系の方が多いという傾向にありました。
また、10社以上と回答した学生も、文系は8.2%、理系は14.1%となっており、こちらも理系の方がより多くの企業のインターンシップに参加していることが分かります。
インターンシップ参加先への不満
同社の2024年卒の調査データでは、インターンシップ参加先に感じた不満としては、「もっと実際の仕事を体験したかった(40%)」という声が最も多く、次いで「もっと働いている人の雰囲気を知りたかった(35%)」「会社・仕事の厳しさ、大変なことなどマイナスな部分も知りたかった(34.4%)」となっています。(*2)これは、コロナの影響で対面での交流機会に制限がある昨今、”リアル”な情報を求める学生が増加していますが、前年よりも対面型のインターンシップが増加したことで、より”リアルな体験”を求める気持ちが強くなっていることが考えられます。
インターンシップ動向を踏まえた今後のポイント
以上の学生動向を踏まえると、秋冬インターンシップを成功させるには、以下のポイントを押さえることが重要と言えます。
①できる限り具体的な仕事体験を行う
インターンシップ参加先への不満に挙がっている通り、多くの学生は「インターンシップで実際の仕事を体験したい」と考えており、インターンシップ=就業体験と考える学生も少なくありません。そんな中、インターンシップという名のもと、採用説明会と同じようなプログラムを実施していては、学生の不満が高まり、結果として採用成果につなげることができません。
そのため、インターンシップには、できる限り具体的な仕事体験を盛り込むことが重要です。また、オンラインで実施する場合も、あるテーマについてディスカッションの上、プレゼンを行ってもらうような「課題解決型」のプログラムを盛り込むことで、仕事の疑似体験をしてもらうことが重要です。
②社員との交流機会を設ける
社会人経験のない学生にとって「何の仕事をするか」と同じくらいに重要な要素が「誰と働くのか」です。そのため、インターンシップの中で多くの社員との交流機会があることは、インターンシップの満足度を高める要因となります。
また、若手社員を中心に交流会を実施することで、より話しやすい雰囲気の上で交流しつつ、入社後の働くイメージや仕事のやりがいを「若手社員の声」として伝えられると良いでしょう。
③会社の魅力・強みだけでなく、あえてマイナス面も伝える
昨今、採用のミスマッチによる早期離職に悩む企業が増加しています。採用ミスマッチの原因はいろいろとありますが、その1つに「入社前にイメージする姿と、実際の現場や働き始めた際の現実のギャップが大きい」ことが挙げられます。
上記を防ぐためにも、会社の魅力・強みだけでなく、あえて会社の弱みや学生にとってネガティブに捉えられる可能性があるような、マイナス面の情報を伝えることで、入社前後のギャップをなくすとともに、誠実な姿勢で採用活動を行っていることをアピールすることが重要です。
なお、マイナス面も伝えすぎると逆効果になる恐れもあるため、「会社の弱み+それを改善するための取り組み」をセットで話すなど、その伝え方や伝える内容については、十分に注意しましょう。

 0120-370-772
0120-370-772